高齢者にとって「スマホは難しそう」「触ったら壊れそう」といったイメージを持つ方は少なくありません。
しかし、スマホは実は正しく使えば非常に便利で、生活の質を大きく向上させてくれる道具です。
この記事では「高齢者にスマホは無理?」という疑問にお答えしつつ、スマホの電源の入れ方や基本操作を【超初心者向け】にわかりやすく丁寧に解説していきます。
スマホを触るのが初めての方でも、この記事を読めば「これならできる」と思っていただけるはずです。
さあ、一緒にスマホ生活の第一歩を踏み出してみましょう。
スマホは本当に高齢者に難しいの?
「スマホ=難しい」という先入観がある理由
多くの高齢者が「スマホは自分には無理」と感じてしまう最大の理由は、見たことのない機械に対する“未知への不安”です。
ガラケー時代のように物理ボタンがあるわけではなく、すべてが画面タッチで操作されるスマホに対し、何をどう触ったらよいのかがわからないという声は非常に多く聞かれます。
また、身近にいる家族や若い世代が当たり前のようにスマホを使っている様子を見て、「自分にはとても無理だ」と感じてしまうことも要因のひとつです。
たとえば、ある70代の女性は「家族が早口で説明してくれても、まったく頭に入らなかった」と言います。
つまり、内容が難しいのではなく、教える側と教わる側のテンポが合っていないことも「難しそう」と感じさせてしまう理由なのです。
使いこなせている高齢者が増えている現実
とはいえ、今やスマホを使いこなしている高齢者も少なくありません。
総務省の調査によると、60代以上のスマホ利用率は年々増加しており、70代でもスマホを使ってYouTubeを観たり、LINEで家族とやりとりする方が急増しています。
たとえば、週に一度の句会の様子をスマホで撮影して仲間に共有している80代の男性や、病院の予約をスマホで済ませる70代の女性など、生活にしっかりスマホが根付いている方も多いのです。
このように、慣れていないからと言って「できない」と決めつける必要はまったくありません。
スマホがあることで広がる生活の楽しみ
スマホを持つことで得られる楽しみや便利さは、年齢に関係なく平等です。
たとえば、LINEで孫の写真がリアルタイムで届くようになったり、昔懐かしい歌謡曲をYouTubeで聴いたり、旅行先をスマホで調べたりと、生活がぐっと豊かになります。
実際に、週末になるとスマホでお気に入りの演歌歌手の動画を検索して楽しんでいるという高齢のご夫婦もいます。
また、災害時の情報収集や緊急連絡手段としても、スマホは非常に役立ちます。
したがって、最初の一歩さえ踏み出せば、スマホは高齢者の心強い味方になってくれるのです。
それでは次に、スマホの基本的な見た目や名称について詳しく見ていきましょう。
まずはここから!スマホの基本的な見た目と名称
スマホの画面やボタンの名前を覚えよう
スマホを使い始める第一歩として、本体の部品の名称を知っておくことはとても大切です。
画面は「タッチパネル」と呼ばれ、指で直接触れることで操作できます。画面の下部には「ホームボタン(物理ボタンがあるタイプのみ)」があり、操作中でも最初の画面に戻ることができます。
また、右側または上部にある小さなボタンは「電源ボタン」です。このボタンは電源のON/OFFや、画面を消すときに使います。
左側にある細長いボタンは「音量ボタン」で、着信音や動画の音量を調整します。
たとえば、ある70代の男性は「このボタンが何なのかがわかっただけで、スマホへの恐怖が和らいだ」と話していました。
このように、まずは見た目と名称に慣れるだけで、心理的なハードルが大きく下がります。
AndroidとiPhoneの違いは?
スマホには「Android(アンドロイド)」と「iPhone(アイフォーン)」という2つの種類があります。
Androidは主に国内の多くのメーカー(富士通、シャープ、ソニーなど)から販売されており、使える機種の種類が豊富です。一方、iPhoneはApple社の製品で、操作画面がシンプルで統一されています。
たとえば、「iPhoneは説明書がなくても直感的に操作できる」と言われることが多いですが、「Androidはカスタマイズ性が高く、らくらくスマホなど高齢者向け機種も多い」のが特長です。
どちらが良い・悪いということはなく、目的や使いやすさで選ぶのがベストです。
ちなみに、60代以上の方に人気が高いのは、見やすさとサポートの充実で定評のある「らくらくスマホ(Android)」です。
スマホを扱う前に知っておきたい操作の基礎
スマホを使う前に知っておくと安心な操作方法があります。それは「タップ」「スワイプ」「長押し」という3つの基本操作です。
・タップ=画面を軽く1回触る ・スワイプ=指を滑らせて画面を動かす ・長押し=画面を2秒ほど押し続ける
この3つの操作を知っていれば、ほとんどのスマホ操作に対応できます。
たとえば、アプリを起動したいときは「タップ」、画面を下にスクロールしたいときは「スワイプ」、アプリを消したいときは「長押し」して削除するなど、シーンごとに使い分けます。
つまり、スマホの操作は特殊なことではなく、「触れ方に名前がついているだけ」なのです。
それでは、いよいよ電源の入れ方・切り方に進みましょう。
電源の入れ方・切り方をやさしく解説
電源ボタンの位置を確認しよう
スマホの電源を入れるには、まず「電源ボタン」の位置を確認する必要があります。
一般的に、電源ボタンはスマホ本体の右側の上のほう、または上部の側面にあります。最近の機種では、本体の右側中央に配置されていることもあります。
ボタンの大きさはあまり目立たず、押しやすい位置にありますが、慣れないうちはどのボタンか迷うこともあるでしょう。
たとえば、ある女性(75歳)は「音量ボタンと間違えて押しても反応しなくて困っていたが、息子に『側面の上の方だよ』と教えてもらってからはすぐに覚えられた」と話していました。
このように、まずはスマホ本体を手に持って、どこにどんなボタンがあるかをしっかり確認することが大切です。
電源を入れると何が表示される?
電源ボタンを2〜3秒ほど長押しすると、スマホが起動します。すると、最初にメーカーのロゴが表示され、その後に「ロック画面」と呼ばれる画面が現れます。
ロック画面には現在の時刻や日付、通知(お知らせ)などが表示され、ロックを解除することでホーム画面に入ることができます。
解除の方法は機種によって異なりますが、「スワイプする」「パスコード(暗証番号)を入力する」「指紋をかざす」などがあります。
たとえば、「娘にプレゼントされたスマホを初めて起動したときに、何が表示されているのかわからず不安になったけど、画面の『上にスワイプ』という文字に従ったら簡単だった」と語る方もいます。
このように、初めての画面は慣れないかもしれませんが、表示される指示に従えば迷うことはありません。
電源を切るときの注意点とコツ
電源を切る方法も、機種によって少し異なりますが、基本的には電源ボタンを長押しすることで「電源オフ」の画面が表示されます。
画面に表示される「電源を切る」や「シャットダウン」といった項目を、指でタップまたはスライドすることで電源がオフになります。
ここで注意したいのが、電源ボタンを短く押しただけでは「画面が暗くなるだけ(スリープ状態)」で、完全に電源が切れたわけではないという点です。
たとえば、「寝る前にスマホのボタンを押したけど、朝までアラームが鳴り続けていてびっくりした」というケースもあります。
そのため、きちんと電源を切りたいときは、「長押し」して表示される画面で操作するようにしましょう。
このような基本操作に慣れてくると、スマホに対する苦手意識がぐっと減ってきます。
では次に、操作に慣れるためのコツを紹介していきましょう。
操作に慣れるにはどうしたらいい?
まずは毎日電源を入れてみよう
スマホ操作に慣れるには、まず「触ること」に抵抗をなくすことが第一歩です。
そのために最も効果的なのが、「毎日電源を入れてみる」ことです。
たとえば、朝起きたらテレビをつけるように、スマホの電源を入れてみる習慣をつけるだけで、自然と使い方に慣れていきます。
はじめは電源の入れ方やロックの解除だけでも構いません。繰り返すことで手の動きが覚えてくるため、緊張感も薄れていきます。
ある80代の女性は「最初は1日1回、電源を入れて時間を見るだけだったけど、気がついたらLINEも使えるようになった」と話してくれました。
このように、スマホは“回数”が自信につながります。最初の一歩はとてもシンプルでよいのです。
困ったときは誰に聞けばいい?
スマホを使っていると、わからないことや戸惑う場面に必ず出会います。
そんなときに頼れる存在を事前に決めておくと、安心して使い続けられます。
一番身近なのは、家族や親しい友人です。LINEでのやり取りを教えてもらったり、写真の送り方を聞いたりと、実際の操作を見せてもらうことで理解が深まります。
また、携帯ショップでは高齢者向けのスマホ教室を実施しているところも多く、少人数でやさしく教えてくれると好評です。
たとえば、ある高齢男性は「娘に聞くと忙しそうで遠慮してしまうが、スマホ教室だと何度でも聞ける」と言って、毎月1回通っているそうです。
加えて、地域の公民館やシニア向けの学習センターでもスマホ講座が開催されていることがあるので、地元情報をチェックしてみるのもおすすめです。
安心して触れる練習モードやサポートアプリ
最近のスマホには、初心者向けの「練習モード」や「サポートアプリ」が用意されている機種もあります。
たとえば、富士通の「らくらくスマホ」には、画面上に「やさしくナビ」や「おまかせ操作説明」があり、操作方法を音声とアニメーションで教えてくれます。
また、「スマホ教室アプリ」や「動画マニュアル」などを使えば、自宅にいながら学習することも可能です。
ある70代の方は「説明書よりも動画の方が頭に入りやすい」と話し、スマホでYouTubeの操作説明を見ながら一つひとつ試していたそうです。
このように、無理のないペースで自分に合った学び方を見つけることが、スマホ操作に慣れる一番の近道です。
では最後に、高齢者でも安心して使えるスマホ選びのポイントと、購入後のサポート体制についてご紹介します。
高齢者向けのスマホ選びとサポート体制
見やすくて使いやすい「らくらくスマホ」とは?
高齢者にとって初めてのスマホ選びは非常に重要です。
その中でも人気が高いのが、NTTドコモの「らくらくスマホ」シリーズです。
この機種は、ボタンが大きくて見やすく、操作画面もシンプルに設計されており、初めてスマホを使う高齢者に配慮された作りになっています。
たとえば、メニュー画面には「電話」「メール」「写真」「インターネット」などが大きな文字で表示され、押す場所が一目でわかります。
さらに「押しやすいボタン」「誤操作防止機能」「音声入力」など、細かいところまで工夫がされているのも特徴です。
ある80代の女性は「このスマホは“私のために作られたんじゃないか”と思った」と語っており、特に“聞きたい言葉を話すとアプリを開いてくれる”音声操作機能に感動したそうです。
つまり、初めてスマホを使う高齢者には、こうした専用機種を選ぶことで、安心してスマホ生活をスタートさせることができます。
購入時に利用できるサポートサービス
スマホを購入する際には、携帯ショップや家電量販店でサポートサービスを積極的に活用することが大切です。
たとえば、購入と同時に「初期設定サポート」や「データ移行サービス」が受けられるほか、必要に応じて「使い方講座」も予約できます。
特に大手キャリア(ドコモ、au、ソフトバンク)では、無料または低価格でシニア向けのスマホ教室を実施しており、基本操作からLINEの使い方まで学べます。
ある男性(74歳)は「ショップのスタッフさんがマンツーマンで教えてくれて、安心できた」と話していました。
また、最近では「オンラインサポート」も充実してきており、自宅にいながらサポートを受けられるサービスも登場しています。
このように、購入時には説明をしっかり聞き、必要に応じてサポートプランを申し込んでおくと安心です。
家族との連携で安心・安全に使えるスマホ生活
スマホは一人で使うものではなく、家族とのつながりを深めるためのツールでもあります。
たとえば、LINEで孫から写真が届いたり、電話の代わりにビデオ通話を楽しんだりと、距離があっても近くに感じられるのがスマホの魅力です。
また、家族が「位置情報共有」や「リモートサポート」機能を設定しておくことで、操作の手助けや安全確認にも役立ちます。
たとえば、ある家庭では「おばあちゃんのスマホに異変があればすぐ通知が来るようにしてある」と言っており、万一の際にも迅速に対応できる仕組みを整えています。
さらに、家族がスマホの使い方を丁寧に教えてあげる時間を持つことは、コミュニケーションの時間にもなり、親子・孫との絆を深める良い機会となるでしょう。
このように、スマホを「自分のもの」としてだけでなく、「家族とつながる道具」として考えることが、安心してスマホを使い続ける秘訣なのです。
それでは最後に、今回の内容をまとめてみましょう。
まとめ
スマホは「高齢者には難しい」というイメージを持たれがちですが、実際には基本的な操作さえ覚えてしまえば、非常に便利で楽しい道具になります。
特に、電源の入れ方や画面の見方、ボタンの名称など、最初に身につけるべきポイントはそれほど多くありません。
また、「らくらくスマホ」など高齢者向けに設計された機種を選ぶことで、操作がさらに簡単になり、不安を軽減できます。
毎日少しずつスマホに触れること、困ったときは無理せず誰かに頼ること、そして自分のペースで習得していくことが、何より大切です。
スマホを使えるようになると、家族とのつながりが深まったり、生活の中での楽しみが増えたりと、多くのプラスの変化が訪れます。
最後に、無理をせず、「今日はここまでできた」という達成感を大切にしながら、少しずつスマホ生活を楽しんでいきましょう。
きっと、スマホはあなたの毎日をより豊かにしてくれる心強いパートナーになるはずです。
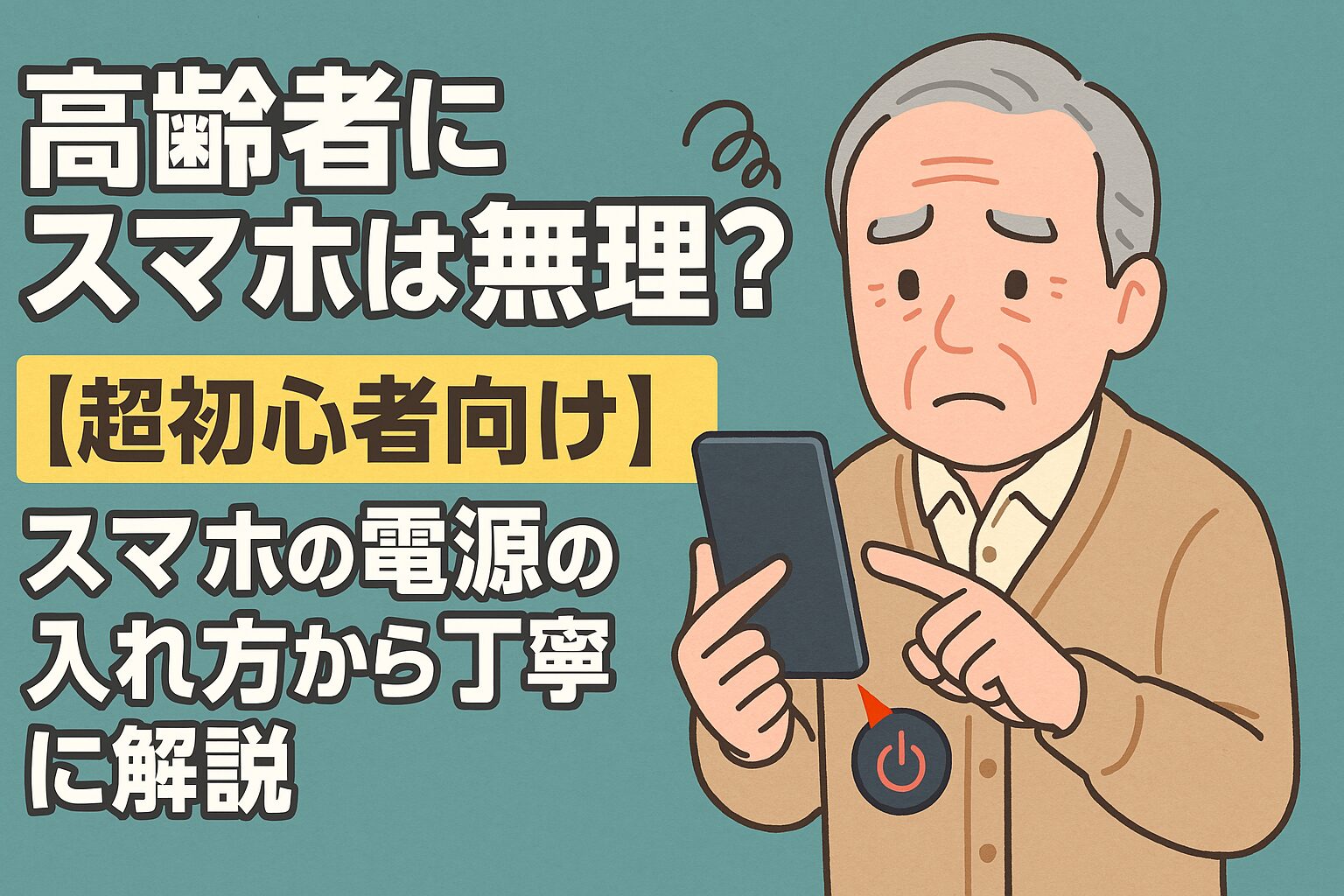

コメント