近年、シニア層を狙った迷惑SMSや迷惑電話の被害が急増しています。特にショートメール(SMS)を利用した詐欺は、スマートフォンの普及に伴ってより巧妙化しており、受信者が無意識のうちに被害に巻き込まれるケースも少なくありません。
この記事では、シニア層に増えている迷惑SMSや迷惑電話の最新の実態と、そのブロック方法や注意点について、実例を交えながら詳しく解説していきます。
スマホの操作に自信がない方でも理解しやすいよう、機種ごとのブロック手順や、アプリの活用法も丁寧に紹介しています。「知らなかった」では済まされない被害を防ぐために、今すぐ対策を始めましょう。
迷惑SMS・電話が急増中!シニア世代が狙われる理由とは?
なぜ今、シニアが標的になりやすいのか
シニア世代が詐欺や迷惑連絡のターゲットになりやすいのには、いくつかの理由があります。
まず大きな要因は、スマートフォンを使い始めたばかりの人が多く、デジタルリテラシーが十分でないケースが目立つことです。つまり、詐欺メッセージや不審な電話を見抜くスキルが未熟な状態で利用しているという点が狙われる原因となっています。
また、家族や友人との連絡を大切にする気持ちが強く、見知らぬ番号や不審なSMSであっても「何かの用事かもしれない」と思って応答してしまう傾向もあります。
たとえば、ある高齢者は「お孫さんが事故に遭った」という偽の電話に驚き、数十万円を振り込んでしまったという事例があります。
加えて、スマホのセキュリティ設定が初期のままであるケースも多く、迷惑連絡を防ぐ術を知らないまま利用していることが多いのです。したがって、まずは現状を知ることが重要です。
どんな内容のSMSや電話が届く?最新の事例を紹介
最近よく報告されているのは、宅配業者や金融機関を装ったSMSです。「荷物の再配達はこちら」や「クレジットカードに不正利用の可能性があります」といった文面にURLが記載され、クリックを誘導する手口が増えています。たとえば、ヤマト運輸をかたる偽SMSでは、リンク先が偽サイトになっており、個人情報を盗まれるという被害が発生しています。
電話では、「還付金があります」「医療費が戻ってきます」など、役所を装う内容が代表的です。高齢者はこうした言葉に敏感なため、信じてしまうリスクが高いといえます。
こうした迷惑連絡は見た目が本物そっくりなことが多く、見分けがつきにくいのが厄介な点です。そのため、形式ではなく“発信元”をしっかり確認することが大切です。
被害にあう前に知っておきたい詐欺手口の特徴
迷惑SMSや電話には、いくつかの共通した特徴があります。たとえば「すぐに対応してください」など、受信者に焦りを感じさせる文言が多く使われています。また、URLのリンクが短縮されているケースや、送信元がアルファベットの羅列になっている場合は特に注意が必要です。
実際に、あるシニア男性は「マイナポイント申請が不完全です」というSMSにだまされ、フィッシングサイトに個人情報を入力してしまいました。結果として、クレジットカードが不正利用される被害に遭っています。
このように、焦りや不安をあおる文面には細心の注意を払うことが必要です。次に、具体的なブロック方法をスマホ機種別に見ていきましょう。
SMSの迷惑メッセージをブロックする方法【スマホ別】
AndroidスマホでのSMSブロック手順
Androidスマートフォンには、端末メーカーによって異なる独自のSMSアプリが搭載されていますが、ほとんどの場合はGoogleの「メッセージ」アプリが利用可能です。迷惑SMSが届いたときは、メッセージを長押しして「ブロック」または「スパムとして報告」を選択するだけでOKです。
たとえば、ある利用者が「楽天カードセンター」を名乗る不審なSMSを受け取った際、Googleメッセージのスパム報告機能を使って即時に対処できました。ブロックした相手からは今後SMSが届かなくなるため、精神的な負担も軽減されます。
ただし、Androidのバージョンやメーカーによって表示が異なることもあるため、事前に自分の機種の操作方法を確認しておくと安心です。
iPhoneでのSMSブロック設定方法
iPhoneを使っている場合は、メッセージアプリを開いて該当のSMSを表示し、右上の連絡先マークをタップ、「情報」→「この発信者をブロック」で完了します。また、設定アプリから「メッセージ」→「不明な差出人をフィルタ」にチェックを入れると、登録していない相手のメッセージを自動で分けて表示してくれます。
たとえば、Apple IDの不正アクセスを装ったSMSに対して、ある女性は「不明な差出人フィルタ機能」をONにしていたことで誤ってURLを開くことを防ぐことができました。ブロックしても通知が届いてしまう場合は設定の見直しが必要です。
なお、迷惑SMSは送信元を偽装してくることもあるため、内容が怪しいと感じたらすぐにブロックしましょう。
ブロック以外の対策アプリの活用もおすすめ
スマホに標準搭載された機能に加えて、セキュリティアプリの活用も有効です。たとえば「トゥルーコーラー(Truecaller)」や「Whoscall」といったアプリは、スパムデータベースに基づいて不審なメッセージや電話を自動で検知し、事前に警告を出してくれます。
実際、ある高齢者の方はWhoscallを使って、「市役所」になりすました詐欺電話を自動で警告表示され、すぐに通話を切ることができたといいます。こうしたアプリは無料でも使える機能が多く、操作も直感的で簡単です。
とはいえ、アプリの導入に不安がある場合は、家族や信頼できる人に設定を手伝ってもらうのも良い方法です。次は、迷惑電話の着信拒否方法について解説します。
迷惑電話をシャットアウト!着信拒否の設定方法
電話番号を個別にブロックする基本のやり方
迷惑電話の着信を防ぐ最も基本的な方法は、電話番号を個別にブロックすることです。Android・iPhone共通で、通話履歴や連絡先から対象の番号をタップし、「ブロック」または「この発信者を着信拒否」に設定するだけで完了します。
たとえば、ある高齢女性が「未納料金があります」という脅迫電話を受けた際、番号をすぐに着信拒否リストに登録したことで、以後は一切の連絡を遮断できました。一度登録すれば、その番号からの着信やSMSは自動的に拒否されます。
ただし、番号を変えて何度もかけてくる業者もあるため、これだけでは完全な対策とはいえません。
スマホの「着信拒否設定」を活用する方法
個別ブロックに加えて、スマホ本体に備わっている「着信拒否設定」を活用することで、より広範囲な対策が可能になります。たとえば、非通知着信を拒否する、特定のエリアコード(市外局番)を制限するなどの方法です。
iPhoneであれば「設定」→「電話」→「不明な発信者を消音」、Androidでは機種によって「通話設定」→「着信拒否」などから細かく調整できます。
こうした設定を知らないまま使い続けていると、迷惑電話のストレスが溜まってしまいます。ゆえに、基本設定を見直すだけでも大きな効果があります。
迷惑電話対策アプリでより安心に!
スマホの標準機能に加えて、迷惑電話を自動でブロックしてくれるアプリもあります。「楽天でんわ」「トビラフォンモバイル」「Whoscall」などが代表的です。これらは迷惑電話データベースと連動しており、着信時に「迷惑の可能性あり」と表示されるため、相手が誰か分からないまま出ることを避けられます。
たとえば、ある男性が「保険の営業」を装った執拗な着信に悩まされていたとき、トビラフォンの利用によって自動的に通話を遮断できるようになり、安心してスマホを使えるようになったという話があります。
こうしたアプリは、自分で着信を判断するストレスを減らし、生活の質を守るのに非常に役立ちます。では次に、こうしたブロック対策だけでは防げない落とし穴について見ていきましょう。
注意!ブロックだけでは防げない落とし穴とは
偽の番号やSMSがすり抜けるケースも
スマートフォンのブロック機能や対策アプリは確かに効果的ですが、完璧ではありません。詐欺業者は年々手口を巧妙化させており、偽装された電話番号やSMSが、ブロックリストをすり抜けて届くこともあるのです。
たとえば、実在する宅配会社や銀行とほぼ同じ番号を偽装したSMSが届き、見た目ではまったく見分けがつかないケースが報告されています。このようなすり抜け型の詐欺は、ブロック機能だけでは防げないため、最終的には受け取った側の「見極め力」が問われます。
それゆえに、内容に違和感があれば無理に開かず、まずは公式サイトや家族に確認する癖をつけることが大切です。
うっかりリンクを押してしまった時の対処法
万が一、怪しいSMSのリンクをタップしてしまった場合も、落ち着いて対処することが重要です。リンク先で何かを入力する前であれば、多くの場合は大きな被害には至りません。
しかし、カード番号や暗証番号、マイナンバーなどを入力してしまった場合は、速やかに該当機関に連絡して利用停止などの手続きを取りましょう。入力直後であれば被害を最小限に抑えられる可能性があります。
たとえば、ある高齢の男性はクレジットカード情報を入力してしまいましたが、気づいてすぐにカード会社に連絡し、カードの利用停止措置を取ることで被害を防ぐことができました。
家族や周囲との情報共有でリスク軽減
最も効果的な防衛策の一つが「情報の共有」です。日常的に家族や近所の人と、受け取った不審なSMSや電話について話し合うだけで、防げるリスクが格段に増えます。
たとえば、「この番号からこんな電話があった」「最近こういうSMSが増えているらしい」といった話題を共有することで、身近な人たちも警戒するようになります。特にシニア世代では、身近な人の体験談が最も信頼されやすいという特徴があります。
では次に、これまで紹介してきた対策をより効果的に活かすために、日常で実践できる具体的な習慣について紹介します。
今すぐできる!シニアが自分の身を守る3つの習慣
不審なSMS・電話は「出ない・触らない・返信しない」
シニア世代が自分の身を守る第一歩は、「出ない・触らない・返信しない」という3つのルールを徹底することです。たとえば、知らない番号からの着信や、見覚えのないSMSに対しては、すぐに対応しないよう心がけましょう。
たとえば、ある女性は「あなたの口座が凍結されました」というSMSを受け取りましたが、すぐに操作せずに息子に相談したことで詐欺を回避できました。このように、一人で判断せず、まずは一呼吸おいて周囲に相談することが重要です。
相手の言葉に急かされると、冷静な判断力が失われやすくなります。落ち着いて、まずは無視することを基本にしましょう。
定期的にスマホの設定を見直そう
スマートフォンは初期設定のまま使い続ける人が多いですが、定期的な見直しが非常に大切です。とくに「不明な発信者の通知設定」や「メッセージのフィルタリング設定」は、定期的に確認しておくことで、知らぬ間にブロック機能がオフになっているなどのトラブルも防げます。
たとえば、半年に一度は「設定」アプリを開いて、迷惑メッセージや電話の対策が有効になっているかをチェックする習慣をつけましょう。スマホのセキュリティ設定も「見直し」が最大の防御力になります。
設定を一度も見直したことがない人は、今すぐ確認することが推奨されます。
困ったときは誰かに相談!一人で抱えないこと
迷惑SMSや電話の対応に悩んだとき、最も避けたいのが「一人で抱え込む」ことです。家族や友人に相談するだけで、問題がスムーズに解決するケースは非常に多いです。
たとえば、ある高齢の男性は詐欺の疑いがあるSMSを受信し、自分で判断できずに地域のスマホ教室に相談したところ、スタッフが対応してくれたことで安心してスマホを使い続けられるようになったそうです。
スマホの使い方は「一人で学ぶもの」ではなく、周囲と一緒に学んでいくものという意識を持つことで、トラブルを未然に防ぐ力がついていきます。次は、これまでの内容を簡潔にまとめます。
まとめ
迷惑SMSや電話は、特にシニア世代を狙って巧妙に仕掛けられています。日々の生活の中で突然届くその一通、その一本の電話が、大きな被害へとつながる可能性があるのです。
今回の記事では、「なぜシニアが狙われやすいのか」から始まり、スマホの機種別ブロック方法、アプリを活用した対策、そしてブロックだけでは不十分な理由まで、段階的に解説しました。
特に注目していただきたいのは、「すぐに反応しない」「設定を見直す」「誰かに相談する」という、日常の中で実践できる3つの習慣です。これは、スマホに不慣れな方でも今日から取り入れられる重要なステップです。
「自分だけは大丈夫」という思い込みは非常に危険です。迷惑SMSや電話は、誰にでも届きます。そして判断を誤れば、被害にあうのは一瞬です。
一方で、基本的な対策を知り、実践するだけで被害の大半は未然に防げます。ご自身だけでなく、大切な家族や友人を守るためにも、ぜひ本記事の内容をシェアしてください。
なお、スマートフォンの設定やアプリの導入が難しい場合は、自治体や携帯会社のサポート窓口、地域のスマホ教室などを利用することも一つの方法です。情報を味方につけることで、日常の安心がぐっと高まります。


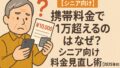
コメント